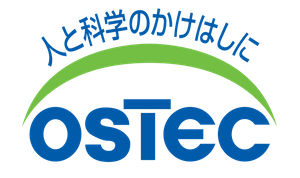フォトニクス技術フォーラム
~未来社会のSociety5.0実現に関わる光・画像システムの調査と普及~
※ Internet Explorer には対応しておりませんので、Microsoft Edge または Google Chrome をご利用ください
フォーラムの概要
・フォトニクス技術の研究開発と活用事例の両面から、広く技術・用途を探り、人的ネットワークも拡げ、今後のフォトニクスのあり方を考えます。
・2025年度は、第9期2年の後半として、画像とそれを実現するデバイス、計測のほか加工への応用など/Society5.0実現に関わる画像システム関連の新規用途として、医療・ヘルスケアと光のような BtoC の新たな用途技術等や新たな測定技術・加工技術などにも注目していきます。
直近イベント
第5回定例研究会を下記の通り開催を予定。
開催日時 : 2026年2月20日(金) 13:30-16:35(研究会)、16:50-18:50(交流会)
研究会テーマ: 「センシング関連」
場 所: (研究会) (一財)大阪科学技術センター Bー102会議室(地下1F)と
オンラインによるハイブリッド開催
題 目:高屈折かつ透明な新材料が拓く次世代光センシング
講演者:東北大学大学院 工学研究科 知能デバイス材料学専攻 助教 石井 暁大 氏
(オンラインよりご講演)
題 目:衛星リモートセンシングを用いた海洋・陸水域の水質・生産性のモニタリングとその将来展望
講演者:名古屋大学 宇宙地球環境研究所 特任教授 石坂 丞二 氏
題 目:フォーメーションフライングによる宇宙ミッションとそのセンサー技術
講演者:東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 中須賀 真一 氏(オンラインよりご講演)
フォトニクス技術フォーラムとは
<背景>
(一財)大阪科学技術センターでは、科学技術の発展と関西産業基盤の強化を目指して、産学官による特定技術領域における情報交流や技術開発等の活動を行っています。
特に、光画像情報システムの構築を目指して、光材料、デバイス、光情報システムを融合的に取り上げた調査研究活動を20年以上にわたって実施してきました。また、この間、これらの成果をもとにした二つの国家プロジェクト「大阪府地域結集型共同研究事業(テラ光情報基盤技術開発)」および「大阪/和泉エリア都市エリア産学官連携促進事業(ナノ構造フォトニクスとその応用)」も実施し、数々の成果を挙げてきました。
本フォーラムは、こうした新しい画像システムの研究開発動向や社会ニーズ等を調査し、光情報技術分野の情報発信拠点としての活動を推進してきた「次世代フォトニクス情報技術フォーラム」(2005年度~2007年度)の活動をもとに、フォーラム組織・体制を衣替えして拡充・強化したものです。そこでは、「光情報技術研究会」と「次世代光学素子研究会」の2つの研究会を設置し、第1~4期(2008年度~2015年度)の研究会活動を実施してきました。
その後、第5期である2016年度からは、これまでの活動成果に基づき、両研究会の学識委員の保有技術を核とした新融合領域開拓等を目標に、傘下2研究会の合同研究会活動を起点に、新融合領域への試みとして、「IoT向けセンサ機器」「インフラ系計測システム」等を取り上げ、光学系処理技術・光学素子技術の両面から新技術に迫る研究会として活動しました。
そして、第6期の活動である2018年度からは、これまでの光情報技術・次世代光学素子研究会を組織的にも一体的な体制に改め、これまでの活動を土台とし、「画像技術とそれを実現するデバイス、および計測技術」に焦点を当てた新たな研究会として、画像システム関連の調査研究を行っております。第7期、第8期は画像システムの実用例に至るまでの話題を取り上げ、コロナ禍の中、社会情勢にあった光・画像の応用技術の普及に努めてまいりました。2024年度より第9期の活動を開始。2025年度は第9紀の後半として活動。これらの活動趣旨や研究者ネットワークにご関心のある方は、是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。<特徴>
1.技術に特化し、自由に議論
- 会員の興味のある技術内容に関して参加者が自由・闊達に議論する場を提供します。
2.広範囲の技術を扱う
- フォトニクス技術フォーラムが取り上げる対象領域は図1に示した通り広範囲の内容について取り上げます。
3.会員のニーズに合わせた柔軟な運営
- 必要な技術は短期間で決着がつくことは考えにくく、様々な研究開発の進捗に伴い変遷することが考えられるため、様々な状況変化に応じてその時々のニーズに合わせて具体的なテーマ設定を柔軟に行っていきます。

2025年度活動内容と運営体制
<活動内容>
1.有識者による講演会・見学会(定例研究会)
- 様々な情報を正しく把握し、共有化することを目指し、各業界、学界等の有識者による講演会を年間5回程度開催します。
- 講演会は原則として来場とZOOMのハイブリッドで行います。
- 各回テーマを決めて2,3件の講演を行います。参加者間の交流と率直な意見交換を図るため、立食形式の交流会も行います。
- 一部は、先進的な取組みをしておられる事業所・大学の見学会とする場合があります。<体制・運営>
本研究会は、大阪科学技術センター技術開発委員会の下に設置され、会長の指導の下、幹事会が具体的な運営を立案します。
<2025年度運営体制>
※所属、役職は 2024 年 5 月の時点での情報で記載しています。
委 員 長 : 粟辻 安浩 京都工芸繊維大学 電気電子工学系 教授
副委員長 : 和田 健司 大阪公立大学 研究推進機構 教授
学識幹事 : 裏 升吾 京都工芸繊維大学 名誉教授
小倉 裕介 大阪大学大学院 情報科学研究科 情報数理学専攻 教授
菊田 久雄 大阪公立大学 名誉教授
宮崎 大介 大阪公立大学大学院 工学研究科 電気電子系専攻 准教授
山田 憲嗣 大阪大学大学院 医学系研究科 特任教授
日坂 真樹 大阪電気通信大学 医療健康科学部 医療科学科 教授
コーディネータ: 北村 佐津木 元(独)科学技術振興機構産学連携展開部 主任調査員
幹 事 : 住友電気工業㈱、ナルックス㈱、パナソニックホールディングス㈱、古野電気㈱、㈱リコー
事 務 局 : (一財)大阪科学技術センター 技術振興部
<会員種別>
- 企業会員:本研究会の目的に賛同する企業(法人)。
- 学識委員:本研究会の活動に資する研究を行っている、大学、国研等の有識者。
- オブザーバー:会員ではないが、本研究会との連携が必要な国、地方自治体、その他関係機関。
<会費>
- 企業会員A:年額275,000円(消費税込み)、OSTEC賛助会員は220,000円(同)
- 企業会員B:年額110,000円(消費税込み)、OSTEC賛助会員は 77,000円(同)
※ 企業A:大企業、中小企業(企業幹事として、幹事会(企画等)に参画可能です)
企業B:中小企業
(人数制限のあるイベント以外は何人でも参加可、飲食費・旅費等は別途徴収)
- 学識会員・オブザーバー:無料(飲食費・旅費等は別途徴収)
会員リスト
学識委員・企業会員(五十音順)
顧 問 :
一岡 芳樹 大阪大学 名誉教授
学識委員 :
市川 裕之 元愛媛大学大学院 准教授
井上 康志 大阪大学大学院 生命機能研究科 教授
太田 淳 奈良先端科学技術大学院大学 理事・副学長
香川 景一郎 静岡大学 電子工学研究所 教授
川田 善正 静岡大学 電子工学研究所 教授
金髙 健二 (国研)産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 高機能ガラスグループ 主任研究員
齋藤 守 (地独)大阪産業技術研究所 森ノ宮センター 研究フェロー
山東 悠介 (地独)大阪産業技術研究所 製品信頼性研究部 室長
篠田 博之 立命館大学 情報理工学部 情報理工学科 教授
谷田 純 大阪大学大学院 情報科学研究科 招へい教授
中野 隆志 (国研)産業技術総合研究所 エレクトロニクス・製造領域 研究部門長
仁田 功一 神戸大学大学院 システム情報学研究科 教授
野村 孝徳 和歌山大学 システム工学部 システム工学科 教授
羽根 一博 東北大学 未来科学技術共同研究センター 特任教授
早崎 芳夫 宇都宮大学 オプティクス教育研究センター 教授
平井 義彦 大阪公立大学大学院 工学研究科 客員教授
的場 修 神戸大学 次世代光散乱イメージング科学研究センター センター長/教授
山田 逸成 摂南大学 理工学部 電気電子工学科 教授
渡辺 歴 立命館大学 理工学部 電気電子工学科 教授
企業会員:
住友電気工業㈱
ナルックス㈱
パナソニックホールディングス㈱
古野電気㈱
ホシデン㈱
㈱リコー
クマリフト㈱
2025年度活動計画
【第9期(2024-2025年度)の活動目標】
「画像技術とそれを実現するデバイス、および計測技術のほか光学に関連する技術」に視点を当て、広く新たな技術・用途を探り、今後の光技術のあり方やその技術限界・境界領域を知ることも目指します。
・技術紹介:最新の技術の紹介&ディスカッション(作り手)
・活用事例紹介:活用事例の紹介&ディスカッション(使い手)
また、「画像技術とそれを実現するデバイス、および計測技術」について、中小企業,ベンチャー等の技術や新たな用途分野の活用事例等を取り上げる等により、多様な意見を交わし、関西の光技術の底上げや地域の産学の連携拡大などにつなげます。
とくに、持続可能な都市・社会環境を実現するための開発目標と技術開発に関する話題を取り上げ、SDGSに向けた光・画像システムにおける技術課題について意見交換を行える場を設けます。
【2025年度の活動内容】
2025年度の「フォトニクス技術フォーラム」の研究会開催予定を表1に示します。上記テーマに関連して、Society5.0実現に関わる画像システム関連の新規用途として、感性に対しての光の効果や影響を、またAR・VR光学系の新技術などBtoCの新たな用途技術等や新たな測定技術・加工技術などにも注目していきます。
なお、2025年度も、ハイブリッド開催(リアル開催とオンライン開催を併用)を基本とした開催形式を試みますが社会情勢によりオンライン開催に変更します。

2025年度活動実績
2025年12月16日(火)第4回定例研究会を下記の通り開催しました。
研究会テーマ: 「AR・VR光学系の新技術」
題 目: 円筒波体積ホログラフィック光学素子を用いたAR導光板講演者: 宇都宮大学 工学部 准教授 茨田 大輔 氏
題 目: デバイスから製品へ―ARグラス実現に向けたメーカーの挑戦
講演者: TDK株式会社 技術・知財本部 応用製品開発センター
ソフトソリューション開発部 アプリケーション開発室 室長 小野松 丈洋 氏
題 目: ホログラフィックコンタクトレンズディスプレイの研究開発状況
講演者: 東京農工大学 大学院 工学研究院 教授 高木 康博 氏
(オンラインよりご講演)参加者 27名 (来場+Zoom)
2025年10月8日(水)第3回定例研究会を下記の通り開催致しました。
研究会テーマ: 「光源の新技術」
題 目: 高輝度テラヘルツ波光源の開発と応用
講演者: 理化学研究所 光量子工学研究センター テラヘルツ光源研究チームチームディレクター 南出 泰亜 氏
題 目: 低毒性元素からなる量子ドットの液相合成と光機能
講演者: 名古屋大学大学院工学研究科/名古屋大学未来社会創造機構量子化学イノベーション研究所 教授 鳥本 司 氏
題 目: 深紫外LEDの配光制御・高出力化とその応用展開
講演者: 国立研究開発法人 情報通信研究機構 未来ICT研究所 神戸フロンティア研究センター
室長 井上 振一郎 氏
参加者 27名 (来場+Zoom)2025年9月2日(火)第2回定例研究会を開催致しました。
研究会テーマ: 「メタサーフェス、メタマテリアル」
題 目: 誘電体メタサーフェスを用いた光通信デバイス講演者: 東京大学 大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 教授 種村 拓夫 氏
題 目: 光・THz波領域における動的制御と構造化:可変メタサーフェスと三次元バルクメタマテリアルの展開
講演者: 東北大学 大学院 工学研究科 ロボティクス専攻 ナノシステム講座 教授 金森 義明 氏
題 目: 社会実装に向けたメタマテリアル技術の開発
講演者: 株式会社村田製作所 技術・事業開発本部 マテリアル技術センター 白井 善晶 氏
参加者 42名 (来場+Zoom)2025年7月22日(火)第1回定例研究会を開催致しました。
研究会テーマ: 「感性と光」
題 目: 住宅の光環境とウェルビーイング講演者: 大阪公立大学大学院 生活科学研究科 居住環境学コース 教授 松下 大輔 氏
題 目: 感性価値創造と視覚メディア
講演者: 関西学院大学 工学部 教授/感性価値創造インスティテュート 所長 長田 典子 氏題 目: 感性ライティングと自然模擬照明
講演者: 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 環境システム技術部
生物応用グループ 山田 旭洋 氏
参加者 50名 (来場+Zoom)2024年度活動実績
2025年3月11日(火) に第5回定例研究会を開催しました。
【研究会テーマ】 「光学技術の新展開」
題 目:「光衛星通信技術の概要と開発動向」講演者: 日本電気㈱ エアロスペース・ナショナルセキュリティー NECフェロー 三好 弘晃 氏
題 目:「コロイド法で作る量子ドットの特徴とディスプレイ等への応用」
講演者: ㈱量子材料 取締役 / (国研)産業技術総合研究所 関西センター 村瀬 至生 氏
題 目:「Computationally-augmentedoptical coherence microscopy: 計算光学による干渉顕微鏡の機能拡張」
講演者: 筑波大学 Computational OpticsGroup 教授 安野 嘉晃 氏
参加者 30名 (来場+Zoom)
2024年12月24日(火) に第4回定例研究会を開催しました。
【研究会テーマ】「光学技術における新たな加工技術」
題 目:「強く集光したベクトルビームによるレーザー微細加工」講演者: 東北大学 多元物質科学研究所 教授 小澤 祐市 氏
題 目:「光を用いたマイクロ・ナノ3Dプリンティング技術の進展」講演者: 横浜国立大学大学院 工学研究科 教授 丸尾 昭二 氏
題 目:「流体デバイスのための三次元微細加工技術&ナノハブ拠点およびARIM事業の紹介」講演者: 京都大学大学院 工学研究科 マイクロエンジニアリング専攻 教授 土屋 智由 氏
参加者 30名 (来場+Zoom)2024年11月14日(木) に第3回定例研究会を開催しました。
【研究会テーマ】「量子情報と光学」
題 目:「量子ネットワークにおけるフォトニクス技術」講演者: 大阪大学 大学院 基礎工学研究科/量子情報・量子生命研究センター 教授/副センター長 山本 俊 氏
題 目:「光量子センシングの現状と展望」講演者: 京都大学 大学院工学研究科 教授 竹内 繁樹 氏
題 目:「シリコンフォトニクスを活用した量子情報処理」講演者: 香川大学 創造工学部 助教 小野 貴史 氏
参加者 49名 (来場+Zoom)
2024年9月3日(火) に第2回定例研究会を開催しました。
【研究会テーマ】「光技術を用いた新たな測定技術」
題 目:「音×光×深層学習による音場の精密イメージング計測」
講演者: NTT コミュニケーション科学基礎研究所 石川 憲治 氏
題 目:「未来の食料生産システムに役立つ農畜水産物の非破壊センシング技術」
講演者: 三重大学大学院 生物資源学研究科 准教授 鈴木 哲仁 氏
題 目:「全ての光を吸収する「暗黒シート」の開発および計測技術への応用・展望」
講演者: (国研)産業技術総合研究所 物理計測標準研究部門 研究グループ長 雨宮 邦招 氏参加者 42名(来場+Zoom)
2024年7月29日(月) に第1回定例研究会を開催しました。
【研究会テーマ】「医療・ヘルスケアと光」
題 目:「機械学習を利用した8K空間分解能シングルピクセルイメージング」
講演者: 大阪大学大学院 工学研究科)准教授 水谷 康弘 氏
題 目:「医療応用へ向けたテラヘルツ波ケミカル顕微鏡の開発」
講演者: 岡山大学大学院 ヘルスシステム統合科学研究科 教授 紀和 利彦 氏
題 目:「遠赤外光PAS(photoacoustic spectroscopy)を用いた非侵襲血糖値計測」
講演者: 公立大学法人富山県立大学 学長 下山 勲 氏参加者 39名(来場+Zoom)